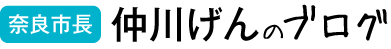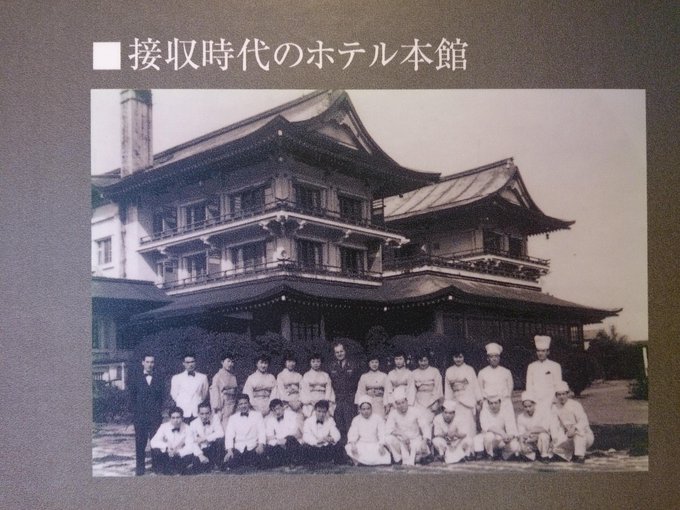全国の自治体のおよそ半数が、2040年には20代 ~30代の女性が半減する「消滅可能性都市」に陥る と警鐘を鳴らした「増田レポート」の衝撃は大きく、6 月議会でも質問が相次ぎました。県内でも市部では 72%減が予測される宇陀市から、僅か1.8%減に留 まる香芝市まで幅が広いのが特徴で、奈良市は 45.6%と12市中6位となっています。
人口減少については以前より指摘されていました が、今回のレポートでは特に地方から都市部への人 口流出が与える影響(社会動態)に着目し、地方の若 者による「人口の再生産力」が街の存続を左右すると しています。
実際に過去10年間の奈良市の人口増減を調べて みると、例えば10年前に20歳~24歳の女性人口は 約1万2千人でしたが、10年後に30歳~34歳になる と約1万人に減っているという状況があります。これ は死亡された方を除けば市外・県外へ転居された方 (厳密に言えば転入者と転出者の差)が多かったと言 えます。
現在、政府では新たな地方戦略の1つとして地方 中枢拠点都市という制度を検討しています。これは 地方の人口20万人以上の都市が核となり、近隣自治 体と共同でより高度なサービスを効率的に提供しよ うとするものです。従来の市町村合併方式では、街の アイデンティティが失われるという危機感から前向 きに進まなかった地域でも、各自治体は存続させた まま、運営面の共通化で合理化メリットを得られると いう利点があります。まずは三大都市圏以外で、かつ 昼夜間人口比率1以上が条件となっていますので、 典型的なベットタウンである奈良市は対象外となり ますが、引き続き国に対し要件緩和を訴えて行きま す。
いずれにしましても、今回発表されたレポートが地 方都市に暮らす私たちに与えたインパクトは大きい ものがありますが、過剰反応も動揺しか生まないと 考えます。しっかりとしたデータに基づき、都市の未 来像を予測してスピード感のある対策を矢継ぎ早に 打つことが重要です。特に女性や若者の活躍しやす い環境を作ることが、人口減少のみならず地方の活 力と革新をもたらす最大の成長戦略とも言えます。 奈良市でもこれまで以上に独自の対策を総合的に講 じて行きたいと思います。
http://www.nakagawagen.net/pdf/newsletter_vol71.pdf