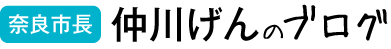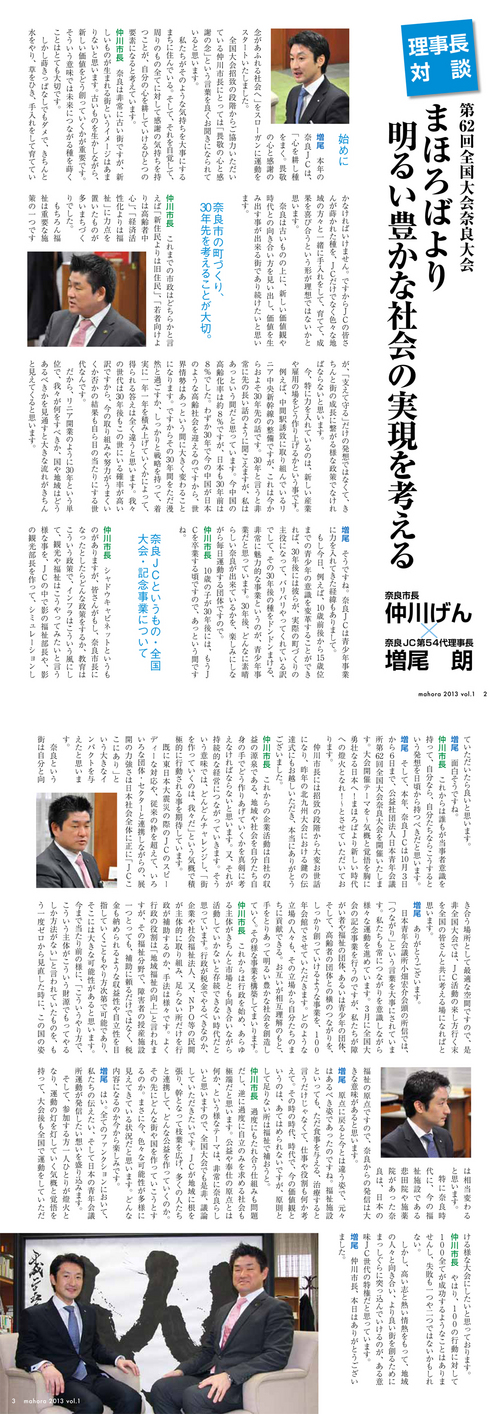先日、中室教育長・杉江教育委員長とこれからの奈良市の教育についてじっくりと話す機会がありました。教育長は中学校の校長経験者ですが、組織マネジメントの視点と進取の精神に溢れた方で、教育政策についての価値観や危機感が私と非常に近く、世間で言われるような市長部局との齟齬は全くと言って良いほどありません。また委員長は長年、大学でミクロ経済学を教えてこられた学識経験者ですが、教育はもちろん、中国古典の研究者として論語に関する書籍を出されるなど、幅広い知見にいつも驚かされます。国でもようやく教育委員会制度の見直しが進み出しましたが、最後は人(誰がなるか)、に依る部分が大きいと思います。
資源の無い日本にとって「最大の資源は人材」とよく言われますが、今後は新興国も含めた激戦の中で、よりグローバルに戦うことのできる人材が求められています。2月に参加した、経済人から研究者・政治家までが一同に集まる「日本版ダボス会議」と呼ばれているG1サミットでも、「2年ほど前からハーバード大学を受験する日本人が急増している」という話題が出るなど、教育行政の課題は経済界にとっても非常に関心の高いテーマとなっています。
これまで日本では長らく、「受験生は東大を頂点とした偏差値ピラミッドの中で少しでも上をめざし、仮に海外の大学に留学するとしても、まずは日本の大学に入ってから」という固定観念がありました。しかし世界の大学ランキングでは東大の9位を最高に、ベスト100には5校が入るのみ(英THE誌)。当の東大も秋入学への全面移行をめざすなど、大学側も世界を意識せざるを得ない状況になっています。受験生の海外志向は、世界に取り残される日本の教育に見切りをつけ、自力で国際競争を勝ち抜く力を身につけようとする姿とも言えます。
私は「教育再生なくして日本の再生は為し得ない」と考え、特に公教育の「質」と「信頼」を高めることを重要課題の1つと位置付けています。具体的には、現在奈良市では通常の県費教員に加え、約100名の市費教員を独自に雇用し、1クラスの定員を小学校低学年では30人、高学年では33人を上限とするきめ細かな教室運営を行っています。
また学力調査についても国による学力基礎調査は小6・中3だけが対象で、しかも昨年度までは一部の学校のみを対象とする抽出調査しか行っていない状況。これでは子どもたちの学習到達度を定期的にモニタリングすることも、時系列で分析することもできません。そこで奈良市では昨年度から独自の取り組みとして、まず小4・中1を対象に追加、さらに今年度からは小4から中3までの6年間・全生徒を対象に毎年実施することにしました。これにより、子どもたちの学習到達度を6年間追跡することが可能になると共に、教員の指導力を定期的にチェックし、研修にフィードバックすることもできます。
教育はよく、「効果がすぐに見えるものではない」と言われますが、その「言い訳」の下で効果の乏しい教育を漫然と続けていては、日本が世界に取り残されるのは自明です。先日、ある経営者の方から「いくら日本人を採用したくても、これだけ海外の人材と差があると、もはや日本人を採用し続けるのは困難だ」という話を聞きました。教育界が取り残されている間に、経済界には大きな危機感が広がっています。
教育は聖域だ、とも言われますが、私は「教育の為の教育」ではダメだと思います。高校や大学を卒業した時に、どんな能力を身につけておくべきか?いま社会や世界はどんな人材を求めているか、をしっかりと捉え、そこから遡って各段階での教育に落とし込む必要があります。「人育ては街育て」と言われますが、これからも「教育改革を通したまちづくり」に向け、新しいチャレンジをどんどん仕掛けていきます。