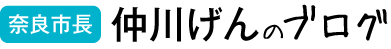2013年3月アーカイブ
奈良市では先日、管理職295名を含む計911名の異動を発令しました。今回の異動にあたっては、単なるローテーションではなく、①限られた人員の中で組織が一丸と なって効率的 ・効果的に動ける体制の確保、②女性や若手職員の積極登用、③新たな市民ニーズへの柔軟な対応の3本を柱 と して取組みました。
まず① については部長級の「統括官」を新設 し24名の部長級職員の取りまとめを担い、縦割り組織に横串を挿すことにします。これは部長と副市長の聞のポストであり、民間企業で言うところの専務にあたります。次に②としてはまず、他市より圧倒的に遅れてきた女性登用をさらに進め、管理職に占める女性比率を11.8%に引き上げました。ちなみに私の就任前は7.5%で したので大きく改善しています。一方、全職員に締める女性比率は13. 2%ですので、さらなる改善に取り組みます。また従来は課長の平均年齢が56歳、部長は退職間際にしかなれないと言われ、管理職としての経験を活かせぬまま、定年を迎える事が多いという問題がありました。そこでこの数年は各ポストに昇格できる年齢条件を緩和し、有能な人材は若くても積極登用する道を聞いています。最後に③では、新斎苑やクリーンセンターなどの喫緊の課題に対応する専門部署の設置や、新エネルギーや奈良町振興、攻める農業といった新たなニ一ズに対応する組織を設けました。特に、従来乏しかった「稼ぐ自治体」としての機能強化を図り、経済活性化や税収増につなげて行きたいと思います。

毎年この季節に行われる恒例行事の1つに「春咲きコンサート」(http://harusaki.jp/)があります。この事業は市内の福祉施設で働くスタッフが中心となり、障害のある、なしに関わらず、全ての人が自分らしく生きられる社会を創ろうと、実行委員会形式で開催されています。1997年からスタートし、今年で何と17回目を迎えます。
この事業がすごいのは、市からの補助金を一切受けていない事。半年ほど前から会議を重ね、本番の準備もボランティアで見事にこなされています。ここ数年は「春咲きの街」と題し、会場の100年会館内に理想の街を表現されています。挨拶の中で私は「皆さんは、『春咲きの街』は本物の街ではなく、作り物の世界だと思われるかもしれない。しかし普段はあまり光が当たらないだけで、私たちが暮らすこの街は多様性に溢れ、障害の有無や年齢に関わらず、いろんな考え方や価値観を持つ人が多彩に織りなす街であり、まさに春咲きの街そのものだ」と述べました。(ちなみに司会は南かおりさん。長年ボランティアで関わっておられます)
奈良市は1972年に全国に先駆けて「福祉都市宣言」を行った街であり、これまでも政策の中心に「福祉のまちづくり」を位置付けてきました。一方、この40年間で高齢化率は8%から25%に急上昇、障害者も年々増加しており、もはや全てを行政が担う事は困難な時代になりました。一方、この間の大きな変化として民の立場で福祉や公益活動を担う取り組みが大きく広がりました。それに伴い、行政の立ち位置は自ずと補完的役割に移行して行くと思います。もちろん、行政としての役割や責任を放棄するのではなく、より当事者による主体的な福祉に転換するという形です。行政も従来のような「支援してあげている」という上から目線を捨て、障害者が暮らしやすい街は、結果として全ての住民にとって優しいまちづくりにつながる、という発想に転換しなければならないと肝に銘じています。
私はこれからの「福祉都市」を考える中では、支える側・支えられる側が一方通行で立場が固定されるのではなく、日常生活で支援を要する人も、出来る範囲で自立し、余力があれば人や社会を支える側にも回る姿が理想だと思います。帰りがけに声をかけて下さった保護者の方からは「うちの子どもは障害はあるが、パソコンは得意。障害があるだけで全ての能力に欠けるかのように思われるのは不本意。健常者だって全ての能力が均一の人なんていないでしょう」と仰ったのが印象的でした。障害者の方にも当然個性があり、好き嫌いがある。ある部分は支援が必要かもしれないが、それはその人のごく一面でしかない、という当たり前のことを社会全体で共有し、尊重できる世の中を創っていかなければなりません。これからの福祉や公共の姿を、改めて考えた一日でした。
来賓あいさつの中で、初代コーチでもある金野自治連合会長が「歴代指導者の中には、がんと闘いながら、病院を抜け出してまで試合に駆けつけた方もいる。多くの方の努力によって、皆さんが全国に行けることを是非知って欲しい」と仰いました。壮行会には保護者や関係者だけでなく、多くの地域の方々が出席され、子どもたちの活躍を地域全体で喜んでおられる様子が伝わってきました。
試合の方は東京の代々木体育館で28日に三重県・群馬県とそれぞれ1回戦を戦うとのこと。健闘を祈ります!

本日は3月定例市議会の予算決算委員会の締めくくりとなる市長総括質疑が行われ、その後来年度予算案に対する委員会採決が行われました。市側が提出した原案に対し、共産党からは組み替え案が、また公明党・民主党と無所属の天野議員からは静脈認証システムの導入経費を減額する(ゼロにする)修正案が出されました。採決の結果、修正案が賛成多数で可決され、その他の予算決算委員会に付託された議案については全て可決となりました。(最終的には22日の本会議での採決で決まります)
静脈認証システムについては、いわゆる中抜けやタイムカードの代打ち等の不祥事を未然に防ぐ対策の1つで、監視カメラの設置や現業職員対象の研修と併せた3本柱の1つです。議会からは「導入したいという気持ちは分かるが、(意識改革等)他にできることがあるのでは」「高度な個人情報を労務管理に用いてはならない」「環境部だけに導入するのであれば平等取扱の原則に反するのでは」などの意見が議案審議を通じて出されていました。
確かに、普通の職場や組織では「そこまでしなくても良いのでは」という指摘ももっともですが、環境部がこれまでにも様々な不祥事を起こしてきた現場であること、また歴史的な問題として市当局の意思や指導が極めて行き届きにくい職場風土であること、職員アンケートの中でもタイムカードの代打ちを指摘する声があったこと等を総合的に判断し、静脈認証システムの導入に踏み切ろうと判断したわけですが、結果として理解を得ることができず大変残念です。
度重なる不祥事に対し、1日も早く職場風土や規範意識を一新し、市民の信頼を取り戻さなければならないという危機感は私だけでなく、真面目に働く多くの現場職員も同じ気持ちだと思います。今後、どのような方策が可能か、改めて検討したいと思います。
今年の7月で私の一期4年の任期が満了となる事に伴い、先日の3月定例市議会代表質問の中で次期市長選への出馬表明を行いました。市政の刷新を掲げ、市長選への立候補を表明したのは4年前の春。積み重なる政治への不信や諦め、街の未来への漠然とした不安や閉塞感に対して、「何とかしてほしい!」と願う市民の切実な想いが、私を市長に選んで頂いた最大の要因であり原動力だったと思います。
そしてこの4年間、私はマニフェストに掲げた「脱利権・しがらみ」「行政のムダ0(ゼロ)」を始めとする様々な改革に着手してきました。市内業者201社が指名停止となる歴史的談合事件を端緒とする入札制度改革、無責任な放漫経営が負の遺産を膨らませ続けてきた土地開発公社の清算、全入居者の2割にも及ぶ市営住宅の長期滞納者に対する明渡し訴訟、家庭系ごみ収集の民間委託や特殊勤務手当の大幅削減などの現業部門改革など、いろんな取り組みを進めてきましたが、いずれも市民感覚に照らし合わせれば「ごく当たり前」のものばかりです。
これらの改革が一定道筋をつける事ができた最大の理由は、1つには時代の変化、もう1つは市政刷新を求める市民の声(世論)が大きな支えとなった事です。「自分には関係ない」と市政に無関心を決め込んだり、「誰がやっても同じ」と諦める、いわゆる「おまかせ民主主義」から卒業し、行政や議会が過ちを犯していないか、本来の役割が機能しているかを住民が自ら監視する事がこれからは重要です。行政もまた、それに応じるべく情報開示を進める必要があります。既にリニューアルした市のホームページでは公共工事の開札録から予算要求資料、議員等からの要望記録まで幅広い情報を公開しています。もちろん、市政改革を支える多くの職員の日々の努力や協力、また議会の理解があったことは言うまでもありません。
この4年間で着実に進み出した市政改革を逆戻りさせることなく、しっかりと定着させ、奈良が持つ潜在的な力・魅力を最大限発揮させ、市民が誇りと感謝を感じ、世界から憧れと敬意をもって称賛される都市へと発展させるべく、引き続き全力で市政運営を担わせていただこうと、再選への挑戦を決意致しました事を、ご報告申し上げます。
先日の3月定例市議会、代表質問の中で次期市長選への出馬表明を行いました。市民感覚とかけ離れた時代錯誤の古い市政の刷新を掲げ、市長選への立候補を表明したのは4年前の春。積み重なる政治への不信や諦め、街の未来への漠然とした不安や閉塞感を、「何とかしてほしい!」と願う市民の切実な想いが、私を市長に選んで頂いた最大の要因であり原動力だと思います。そしてこの4年間、私はマニフェストに掲げた「脱刺権・しがらみ」 「行政のムダ0 (ぜ口) 」を始めとする様々な改革に着手してきました。市内業者201社が指名停止となる歴史的談合事件を端緒とする入札制度改革、無責任な放漫経営が負の遺産を膨らませ続けてきた土地開発公社の清算、全入居者の2割にも及ぶ市営住宅の長期滞納者に対する明渡し訴訟、家庭系ごみ収集の民間委託や特殊勤務手当の大幅削減などの現業部門改革など、いろんな取り組みを進めてきましたが、いずれも市民感覚と照らし合わせると「ごく当たり前」のものばかりです。
これらの改革が一定道筋をつける事がで きた最大の理由は、1つには時代の変化、もう1つは市政刷新を求める市民の声(世論)が大きな支えとなった事です。 「自分には関係ない」と市政に無関心を決め込んだり、「誰がやっても同じ」と諦める、いわゆる「おまかせ民主主義」から卒業し、行政や議会が過ちを犯していないか、本来の役割が機能しているかを住民が自ら監視する事がこれからは重要です。この4年間で着実に進み出した市政改草を逆戻りさせることなく、しっかりと定着させ、奈良が持つ潜在的な力・魅力を最大限発揮させ、市民が誇りと感謝を感じ、世界から憧れと敬意をもって称賛される都市へと発展させるべく、引き続き全力で市政運営を担わせて頂きたいと思います。
先日の記事でもご報告しました通り、マニフェストの「医師・看護師不足対策」は順調に進んでいます。しかし市立病院の建替えに伴う機能拡充や、市内全域での慢性的な看護師不足にも抜本的な対策が必要となることから市独自の看護専門学校を設置するべく、準備を進めてきました。開校にあたっては学校建設の初期投資や毎年の運営経費の負担に加え、専門課程を指導する教員や実習現場の確保が大きな課題となります。そこで現在市立奈良病院の管理者であり、他市での看護学校運営実績を持つ地域医療振興協会の全面的な協力を受け、ようやく今春の開校を迎えることになりました。今回は協会が建設し、春から市が借り受ける予定の学校施設が完成しましたので、その概要をお伝えします。

教室の様子(教壇上は市立病院の西尾管理者)
1学年40名の3学年制の規模となります。

校長予定者の菅さんによる施設案内

明るく開放的なテラス

図書室には専門書から一般教養まで幅広く蔵書が並んでいます

地階には200名が収容できるホールもあります。市民向け健康講座等での活用も可能です。
このような恵まれた環境の中で、これからの奈良の地域医療を支える人材が一人でも多く巣立ってくれることを願っています。