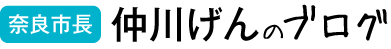奈良市では度重なる不祥事を受け、6月に弁護士3名で構成する「奈良市職員アンケート調査委員会」を立ち上げ、3046名の全職員を対象に記名式で情報提供を求めました。その結果、全回答者2778名のうち、公金の取り扱いに関する不祥事は53名(うち7名は具体的記載なし)、その他の不祥事は435名(うち7名は具体的記載なし)から「心当たりがある」との回答が寄せられました。問題が発生した要因としては、「個人の資質」が83%で最多ですが、「管理体制」 (50%)や「職場風土」 (39%)もあり、今後の課題が浮 き彫りになりました。市では今後事案ごとに追加調査の必要性を判断し、委員とも相談しながらしっかりと事実確認を行う予定です。当然問題が明らかになれば処分等、厳しい対応をして参ります。
一方で、回答者の8割以上が「不祥事をなくすためにどうすればよいと思うか」の設問に回答しており、そのボリュームは160ペー ジにも及びます。問題を起こす職員がいる一方、圧倒的多数の職員は不祥事に対して真剣に捉え、自分たちの努力で体質改善を図ろうと高い意識を持っていることが伺えました。
今回のアンケートに対しては「他人の悪口を告げ口するようなアンケートは職員を不安にさせるだけだ」と いう批判 もありましたが、問題を放置していては、いつまでたっても不祥事が繰り返されるだけで根本的な解決にはなりません。これまでの奈良市の「先送り体質・見て見ぬふり体質」を今改革しなければ、二度とチャ ンスは無いと考え実行しました。これからは全職員がしっかりとした現状認識を持ち、 いかに早く「脱不祥事体質」を達成するかが勝負だと考えています。
2012年10月アーカイブ
奈良市では不祥事を起こさない組織体制の構築に向け、外部の弁護士3名で構成する「奈良市職員アンケート調査委員会」を6月に立ち上げ、3046名の全職員を対象に記名式で情報提供を求めました。これまでは問題が発覚してから対処する事後対応が専らでしたが、不祥事の芽を事前に察知し、未然に防ぐ事が重要だと考えました。そこで本アンケートでは、1)公金の取扱に関するもの、2)それ以外、を対象に「不祥事や市民の信用失墜につながる恐れのあるある事案」を知っているかどうかを問いました。
結果としては全2778名のうち、公金の取り扱いに関する不祥事情報は53名(うち7名は具体的記載なし)、その他の不祥事情報は435名(うち7名は具体的記載なし)から「心当たりがある」との回答が寄せられました。寄せられた情報は原則として、情報提供者やその周囲へのヒアリングまでを委員会が行い、その後の追加調査や処分等については市側で行うこととしています。問題が発生した要因としては、「個人の資質」が83%で最多ですが、「管理体制」(50%)や「職場風土」(39%)もあり、今後の検討課題となりました。
不祥事につながる具体的な情報としては
・入札に関する問題
・国の調査費の不正流用の可能性
・タイムカードの不正代打の可能性
・喫煙等による頻繁な職場離脱や遅刻、等勤務態度に関する指摘、等が挙がりました。
市では今後、個別事案ごとに追加調査の必要性を判断し、3名の委員(弁護士)とも相談しながらしっかりと事実確認を行う予定です。当然、問題事案が明らかになれば処分等、厳しい対応をして参ります。
一方で、83%もの職員が「不祥事をなくすためにどうすればよいと思うか」の設問に回答しており、そのボリュームは160ページにも及びます。問題を起こす職員がいる一方、圧倒的多数の職員は不祥事に対して真剣に捉え、自分たちの努力で体質改善を図ろうと高い意識を持っていることが伺えました。この点については委員の皆さんも私も同感で、今後の内発的な信頼回復に希望が持てる結果だったと感じています。
行政だけでなく、企業等も含めた全ての「組織」は、できることであれば不祥事は表沙汰にしたくない、と考える風潮がまだあります。議会の一部からも、他人の悪口を告げ口するようなアンケートは職員を不安にさせるだけだ、との批判もありました。しかし私は、問題があるにも関わらず放置していては、いつまでたっても不祥事が繰り返されるだけであり、根本的な解決にならないと思います。その点では、これまでの奈良市は、正に「先送り・見て見ぬふり体質」だったと言えます。しかしこれからは全職員がしっかりとした現状認識を持ち、一刻も早く「脱不祥事体質」を達成するかが勝負だと考えています。今回の報告書は全体ではなくサマリーとして公開しています。
詳しくはアンケート調査委のページからご覧ください。
(下段、調査報告書サマリー版・設問5回答一覧)
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1340933790865/index.html
奈良市では10月より一部窓口業務について、休日開庁を行う事になりました。従来は年度替わりの時期に臨時開庁を行っていましたが、今後は恒常的に開庁することになります。先日7日(日)が初めての休日開庁となりましたが、本庁市民課で51件、西部出張所住民課で42件の利用がありました。主な内容としては住民票の写し発行が21件(本庁・西部計、以下同じ)、印鑑証明書の発行が20件、印鑑登録手続きが12件、転入届が5件、就学事務が3件などとなっています。対象業務や窓口は当面限りがありますが、今後は利用状況やニーズを見ながら随時拡大も検討していきたいと考えています。
■受付日時
第1・第3日曜日の9:00~13:00
■開庁窓口
本庁市民課・西部出張所住民課
■受付内容(主なもの)
転入や転出等の住民異動届・印鑑登録
住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の交付
■問合せ先
市民生活部市民課(0742-34-4730)
この紙面でも何度も取り上げてきた奈良市の特殊勤務手当の見直し案が、ようやく9月議会で可決されま した。3月議会での否決を受け、改めて全ての特勤手当を見直した結果、現行の30種から16種に再編整理するとともに、支給額ベースでは年額約3億円から約3000万円へと9割カ ットする案を再提案しました。3月議案との違いは見直し対象を環境部以外の部署まで広げた事、また一部手当については最大1年半の激変緩和措置を設けた事です。今回の制度改革により、全国一高いと批判を受けていた環境部の手当が大幅に改善されることになります。
一方、職員の平均給与(年収ベース)では、全職員平均が約688万円に対し、清掃職員は約774万円と100万円近い差があります。この要因の1つが特勤手当ですが、も う1つの要因が時間外手当(いわゆる残業代)です。奈良市では年間約13億円の時間外手当が発生していますが、これは他の中核市よりも高い水準です。環境部に関しては一人当たり平均363時間と、全職員平均の222時間と比べ1.6倍となっています。確かにごみ関連業務は祝日も休むことができない為、手当を支給して業務に当たらせている事も増加要因の1つです。しかし業務内容をより仔細に検証していくと、いくつかの必要性の乏しい残業が半ば既得権化している実態が明らかとなりました。例えば通常勤務終了後に、ごみの分別 を呼び掛ける放送を流しながら市内をパッ力一車で巡回するようなものは、 誰の目にも人件費 とガソリン代の二重のムダと映ります。しかし、実際にはこれまで誰も手が付けられなかった訳です。この状態に対し8月からは収集3課における残業対象業務の見直しを行いました。予想を上回る大きな抵抗もありましたが、結果として、8月9月実績では対前年比で半減するに至っています。今後も不断の努力で見直しに取り組んで行きます。
金曜日の本会議をもって、9月定例市議会が閉会しました。毎年9月議会は前年度の決算審査がありますが、今年は議会改革の一環として初めて分科会(総務・観光文教水道・厚生消防・市民環境・建設)に分かれて審査が行われました。既に通常の議案については常任委員会へ付託する形となっていましたので、大きな混乱も無く理事者側も対応できたように思います。大きく変わった点としては、議場で予算決算委員会が行われるようになったこと。ボリュームのある案件を一括で審議するのではなく、分野ごとに細分化し、より丁寧に議論しようとする制度改革は、理事者側としても意識改革を迫られる事もあり、非常に効果的だと考えています。なお、提出した議案については、議会のご理解により全て可決・承認して頂くことが出来ました。
今議会での最大の争点は、特殊勤務手当の見直し案です。このブログでも何度か取り上げてきましたが、年間約3億円の同手当ては、特に環境部に関しては全国で最も高額ということもあり、なんとしても改革しなければならない問題でした。本年3月議会に半減案を提案した際には結果として否決となりましたが、その後改めて抜本的な見直しを行い、今回の9月議会での再提案となりました。
詳細は過去の記事参照
http://www.nakagawagen.net/blog/2012/04/post-153.php
主な変更点としては、一部手当てに関しては最大1年半の激変緩和措置を講じる点と、特に危険な作業等については手当の存続・新設も含めた見直しを行った点です。手当ての改正は10月1日より実施され、来年度末の緩和措置期間終了後にはおよそ9割の費用が削減できることになります。今後は、これまで手当てという「給料外のインセンティブ」によって運営してきた収集業務を早急に見直し、体制の再構築に取り組んで行きます。