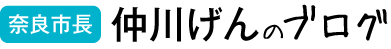このイベントはJATA(日本旅行業協会)が毎年東京で開催されており、今年度は過去最多の12万5989人が来場した「アジア最大規模の旅行見本市」です。奈良市は昨年から出展していますが、今年度は初の単独ブースを設け、観光協会や奈良市東京観光オフィスと連携して大々的にPRを行いました。
2012年9月アーカイブ
このイベントはJATA(日本旅行業協会)が毎年東京で開催されており、今年度は過去最多の12万5989人が来場した「アジア最大規模の旅行見本市」です。奈良市は昨年から出展していますが、今年度は初の単独ブースを設け、観光協会や奈良市東京観光オフィスと連携して大々的にPRを行いました。
奈良市では、市民の皆さんに身近に農業を体験してもらうため、農地を貸し出す「奈良市ふれあい交流ファーム体験事業」を開始します。最近は企業等を退職されたシニア世代だけでなく、若者の間でも農業が静かなブームとなっています。食の安全性への関心はもちろん、自分の手で育てた農作物を家族や友人に喜んでもらえる魅力は代えがたいものがあります。
一方、初心者にとっては農地をどこで探せばよいか、どのように作物を育てればよいか等、分からない点が多々あり、「興味はあるが中々実現できない」という声も聞きます。そこで、今回の事業では、地元の阪原営農組合の方々が耕作指導や体験のサポートをするとともに、トイレや駐車場といった受入施設の開放にご協力いただくことになりました。
申し込みは団体となっていますが、個人(1人)でなければ構いませんので、ぜひご友人やご近所の方々と一緒にお申し込み下さい。
(既に募集を開始していますので、空き状況は下記農林課までお問合せ下さい)
■募集内容
奈良市ふれあい交流ファーム10区画(1区画:約100㎡)
■所在地
奈良市阪原町5428番
現地写真はこちらのリンクから
http://twitter.com/naracity_agri/status/240364914739388416/photo/1
■貸付条件
(1) 市内在住の農業を営まない都市地域住民複数人で構成された団体、グループ等
(2) 1団体につき、1区画
※申込者が区画数に満たないときは、2区画まで貸し付けをします。
■貸付期間
1年間 (今年度は、平成24年10月1日~平成25年3月31日)
■利用料
1区画:年額12,000円
■問い合わせ
奈良市観光経済部農林課(0742-34-5142)
8月5日に早稲田大学で行われた「マニフェスト・サミット2012~地域から新しい日本を~」にパネリストとして参加しました。

マニフェストと言えば既に国政のみならず地方自治体の首長選挙でも相当浸透してきた感がありますが、今回のサミットではいずれもマニフェスト型選挙で当選した一期目の首長4名(左から清水勇人さいたま市長・田辺信宏静岡市長・北川早大教授・山中光茂松坂市長と私)が登壇し、市政への取り入れ方や運用面での課題について議論しました。
マニフェストは元々、180年ほど前にイギリスで採り入れられた選挙公約がルーツと言われ、日本では元三重県知事の北川正恭氏の提唱による「ローカル・マニフェスト運動」が先駆けとして知られています。一般的にマニフェストは政党によるものと地方首長によるものに大別されますが、国政では掲げた公約が実現されないことが常態化していることもあり、有権者の意識も正直「半信半疑」といったところかもしれません。
一方、地方では国と異なり二元代表制であるため、選挙で直接住民から選ばれた首長が、自ら掲げた政策を自分の判断で実行することが可能です。今回のサミットでも、各市において着実に公約が実現している様子が伺えました。反面、課題や悩みとしては「議会の反対で実現できなかった」「職員が他人事のような意識が強い」「既存の総合計画との整合性を図るのに苦労があった」等の意見がありました。奈良市でも毎年秋に市民だよりでマニフェストの進捗状況を報告していますが、他市では別冊の資料を全戸配布するなど、意欲的な取組みがあり刺激を受けました。

「お願いから約束へ」選挙の形が変わり、政策本位の候補者選択が浸透する中で、ベースとなるのはやはり信頼関係です。市民との約束を全力で実現する政治を、市民がしっかりとチェックし、時には苦言を呈すことが「良い政治」を築き上げる唯一の方策だと考えます。
最近のニュースレター記事より(一部、加筆修正)
日々の市政運営の中で、最も難しいと感じるのは多様な市民の声をどのように把握し、政策に反映するかという点です。37万人もの声を1つ残らず汲み上げる事は不可能だとしても、困難な状況にある人や意見表明の機会が与えられていない人の「声なき声」をいかに受け止めるかは重要な問題です。
マニフェストには掲載はしていませんが、私は就任以来、各種委員会・審議会を始め、市の管理職への積極的な女性登用を目標としています。現在、地方自治法第202条の3に基づく審議会等における女性委員の比率は27.3%と、中核市41市中24番目となっています。この中には防災会議のように従来は女性委員がゼロであったものもありますが、新たに委員定数を増やし女性の視点を取り入れています。
また職員に占める役付職員比率(係長級以上)では平成24年度が17.9%と、就任前(15.0%)に比べ着実に改善し始めています。(地方行財政調査会調べ)しかし全職員に占める女性比率が43.3%であることを考えれば、まだ十分とは言えません。
一方、投票権を持たない子どもたちの声も行政に届きにくいものの一つです。先日、市内のある高校で3年生を対象に授業をさせて頂く機会を頂きました。内容は事前学習の中で奈良市の予算や基礎データを分析してもらい、その後「自分が市長だったら」という仮定で自由に政策提言をするというものです。
最初は、「高校生といえば難しい年頃で、市政に対する意見もあまり出ないのでは?」と考えていましたが、日常生活の中で気づいた社会の矛盾や建設的な改善提案が多数寄せられ、私も新鮮な刺激を受けました。実際にこの時の提言がきっかけとなり、今年の夏、中央図書館と西部図書館に自習室を設置する等、施策につながっているものもあります。(以下、記者発表PDF資料)http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1326348377655/files/s240724_07.pdf
街の未来を担う彼らが、今の大人社会をどのように見ているか。声なき声に最大限の想像力を働かせ、日々の市政運営の中で常に意識していきたいと考えています。