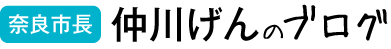1月20日、山本清前奈良市議会議長が贈賄申し込み容疑で大阪地検特捜部に逮捕されました。昨年6月の議長選以降、市政を混乱に陥れた事件は最悪の結果となりました。所属会派である政翔会の関与についても引き続き捜査が行われるとのことですが、改めて3年前の夏、皆さんが一票を投 じた議員が日々どのよ う な仕事をしているか、大きな関心をお持ち頂ければと思います。選挙の時だけ市民の前に現れ、耳触りの良い事を言う。次に会うのは4年後、という話もありますが、政治腐敗の最終責任は有権者にあるのも事実です。一部の利益だけを守ろうとするのではな く、出来ること と 出来ないことをはっきりと線引きをし、市民全体の利益を考える真の政治家がもっと増えることを願います。
24日に招集 された第180回通常国会では、社会保障と税の一体改革が最大のテーマとな りますが、与野党ともに必要な事は、 国民から嫌われる政策や選挙に不利な議論も避けずに正論対正論でしっかりと討議を尽くす事です。私は社会保障と税を一体的に議論する事から始めるのではなく、あらゆる財源確保策の最後の手段に税は位置づけるべきであると考えます。その意味で、年明けから一気に加速してきた公務員給与や議員定数カットはまず「いの一 番」にやり切る覚悟が必要です。さらに我が国最大のムダである、国を頂点とした官僚機構を抜本的に見直すべきです。なぜ公務員が必要か?どこまでを行政が担うべきか?その財源は誰が(どの世代が)負担すべきか?いずれも子どもの質問のように聞こえますが、今の日本が問われている大きなテー マです。 これまでの行政や自治体のあり方を、もう一度すべての国民が我が事 と して考えることで、本来のあるべき姿が見えてきます。国も地方も大転換が求められる中、どちらが先に国民の信頼を取り戻し、次世代に向けた新たな体制を築くことができるか?奈良市も最後尾から猛追していきます。
2012年1月アーカイブ
21日(土) に奈良市としては始めてとなる、大規模な実践型防災訓練を行いました。従来は毎年秋に学識経験者を講師に招き「防災講演会」を行っていましたが、昨年の東日本大震災や紀伊半島大水害を目の当たりにし、より実践的で即応性のある訓練に変更したものです。今回の訓練では所管の市民安全課をはじめ、今年度から防災担当者として着任した退職自衛官が中心となり、災害対策本部のレイアウトから本部会議の進行手順まで細部にわたって準備を行い、まさに本番さながらの緊張感のある訓練となりました。
内容は9月のある日に「台風28号」が市内を襲った、という仮説のシナリオに沿い、市長を本部長とする災害対策本部を設置。本部会議を開催し、支援対策部や保健救護部等9つの部から順次現状報告を受けた上で、今後の対策を指示しました。
今回は事前に準備したシナリオがあったため、スムーズに情報共有や指示ができましたが、いざ本番でどこまで即応できるかが問われます。私も含め、各責任者が1つ1つの動きを考えなくても自然に体が動くようになるには、継続的な訓練が必要だと実感しました。また各部の対応策に関しても、今回の訓練で新たに見えてきた検討課題も複数あり、今後は関係団体との連携も含め、さらに実践的な訓練を行っていきたいと考えています。
少し遡りますが、14日(土)に奈良県文化会館で、生駒の山下真市長・橿原の森下豊市長と私の3市長が登壇する環境シンポジウムが開催されました。これは県内で活動する環境団体「サークルおてんとさん」の主催で、基調講演は気候ネットワークの浅岡美恵代表が世界の温暖化対策の最新事情を報告。その後、3市長が各市の環境政策を発表する事になりましたので、私もマニフェストで掲げた公共交通機関のエコ化の取り組み等を紹介させていただきました。

3市とも、それぞれに独自の取り組みを行っている事が分かりましたが、やはり生駒市は以前から環境自治体をめざしていることもあり、一歩先を行っているように感じました。
後半のパネルディスカッションでは、森下市長が医師としての視点も活かし、「環境にやさしい住宅は健康にも良い」との説を紹介され、山下市長は「ごみ焼却施設等は自治体間の広域連携が重要」と発言されました。奈良市としては、「環境にやさしい観光都市をめざしてさらに取り組みを進めたい」という主旨の発言を行いました。

環境問題は、私も子育て・観光と並び、3大重点分野に位置づけている事もあり、今後近隣市との連携も積極的に探っていきたいと思います。
奈良市ではこれまで県下13の消防本部を一元化することを目的とした、奈良県消防広域化協議会の会長市として組織の広域化(統合化)をめざしてきました。これは国の方針に基づくもので、広域化により管理部門や通信部門のスケールメリットが生まれ、維持管理コストの削減とともに消防力の強化につながる効果が期待されています。
一方、検討を進める中で、これまで各本部が独自の予算で取得・整備してきた車両や機器等の財産の帰属や、年収ベースで最大約150万円の格差がある職員給与や手当の一元化等、いくつもの課題が見えてきました。特に広域化に伴って必要となる約30億円の臨時的経費に関しては、広域化を主導する国や県の負担がほとんどなく、構成する各自治体で按分した場合、奈良市の負担が非常に重くなることがネックとなります。
以上の理由から、奈良市としては県下一元化の消防広域化からは脱退せざるを得ないと判断し、先日開かれた会合でその意向を表明しました。今後は単独での活動を基本としますが、近隣自治体との個別連携については、具体的な効果・メリットが見えれば改めて検討していきたいと考えています。
2012年がスタ ー卜しま した。 昨年は度重なる天災と、 職員不祥事や議会の賄賂問題を始めとした人災が続き、落ち着く事の無い一年間でした。今年はしっかりと問題と向き合い、着実に組織風土を浄化していきたいと思います。 1月は何かと 行事の多い月ですが、 去る8日には恒例の奈良市消防出初式が行われました。昨年の東日本大震災を踏まえ、 いざという 時に市民の生命と財産を守る消防活動には、大きな期待が寄せられており、多くの参加者が来場しました。奈良市ではこれまで県下13の消防本部を一元化すべ く、奈良県消防広域化協議会の会長市として組織の広域化(統合化)をめざしてきました。これは国の方針に基づくもので、広域化により管理部門や通信部門のスケールメ リ ットが生まれ、 維持管理コス トの削減と ともに消防力の強化につながる効果が期待されています。 一 方、 検討を進める中で、これまで各本部が独自の予算で取得 ・ 整備 して きた車両や機器等の財産の帰属や、年収ベー スで最大約150万円の格差がある職員給与や手当の一元化等、 いくつもの課題が見えて きま した。特に広域化に伴って必要となる約30億円の臨時的経費に関しては、広域化を主導する国や県の負担がほとんどなく、構成する各自治体で按分した場合、奈良市の負担が非常に重くなるととがネックとなります。また、正規職員である消防職員は一元化で きても、地域ごとに活動する消防団は従来通りであるため、現場でのスムーズな連携には不安が残ります。以上の理由から、奈良市としては県下一元化の消防広域化からは脱退せざるを得ないと判断し、先日聞かれた会合でその意向を表明しました。粁余曲折はありましたが、最終的に奈良市民にとって最善の方策であると判断しました。
今週末に、私を始め、県内3市長が登壇するシンポジウムが行われますので、ご案内致します。以下転載
シンポジウム
「奈良の市長たちが語るこれからの環境政策」
今まで豊かに使ってきたエネルギーに対する意識は大きく変わりました。
これから私たちはエネルギーや温暖化対策をどうすすめていけばよいのか、一緒に考えたいと思います。
日時:2012年1 月14 日(土) 13 時~16 時30 分
会場: 奈良県文化会館2階AB集会室(近鉄奈良駅より徒歩5分)
参加費: 無料
◎基調報告 「温暖化対策の地域・自治体の役割」
浅岡 美恵 気候ネットワーク代表
◎ディスカッション
パネリスト
仲川 げん 奈良市長
森下 豊 橿原市長
山下 真 生駒市長
清水 順子 サークルおてんとさん代表
コーディネーター
田浦 健朗 気候ネットワーク事務局長
主催:サークルおてんとさん
協力:気候ネットワーク 奈良県地球温暖化防止活動推進センター
後援:奈良県 奈良市 橿原市 生駒市 奈良県緑化推進協会
奈良県生協連 ならコープ 奈良NPOセンター
奈良環境カウンセラー協会 温暖化防止ネットワーク関西
問合せ:サークルおてんとさん(倉本 090-7097-6604)
URL:http://www.geocities.jp/otentsan/
昨日より今年の業務がスタートしました。昨年は東日本大震災や紀伊半島大水害といった天災に加え、市職員による公金着服事件や、議会における議長選贈賄申し込み事件等、市政における不祥事が相次ぎました。
これまでも平成18年のいわゆる「中川事件」(収集課の職員が長期病休中に、身内の経営する建設会社の営業活動を行なっていた事件。免職)や中抜け問題等、度重なる問題は「不祥事のデパート」(週刊ダイヤモンド)と評されるなど、全国的にも酷い状態が指摘されてきました。
昨年末には一年を振り返り、「浄」の一字で再発防止に向けた思いを掲げました。不祥事を根絶するためには、懲戒処分の基準をより厳しくする、いわば「強権発動的」要素と共に、職員自らが体質改善しようとする「内発的浄化」が重要だと考えます。
昨日の仕事始め式の訓示でも、失った信頼を取り戻す作業は長い道のりだが、市民が再び市役所に対し、希望と可能性を感じていただけるよう、全職員が一丸となって意識を高めていこう、と伝えました。