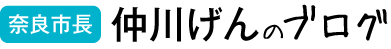国家公務員給与の引き下げに関する人事院勧告の取扱が議論にな っています。今回は東日本大震災に起因する財源確保が大義となっていますが、これまでも厚遇と身分保障に対しては根強い批判がありました。一方で国と地方を比較すると、奈良市を始め、各地方自治体では独自の給与力ットに既に着手していますが、国家公務員においてはこれまでも人勧以上の削減は手つかずの状態でした。これは政治家も同じで、地方議員の定数 ・給与力ッ卜はもはや当た り前ですが、国会議員の定数(現在722名)削減は過去10年間でわずか10名であり、給与カットも半年で元に戻すというお手盛り状態となっています。これからの時代、地方もさらに身を切る努力が必要ですが、国の率先した行革なしの増税論議は頂けないというのが実感です。
とはいえ、奈良市では平成27年までに約111億円の財源不足が予想され、さらなる行革に取り組まなければなりません。昨年 ・ 一昨年と実施した事業仕分けでは、2年間で約25億円の財源捻出に成功しましたが、同じ手法がいつまでも通用する訳ではありません。そこで今年度は「事業・事務の総点検」と銘打ち、事業仕分けでは見えてこなかったムダなコストを徹底的に洗い直す作業に取り組んでいます。例えば、直接事業費はわずかであっても、膨大な人件費がかかっている事業をフルコスト基準で再評価を行う事、また事業目的は問題なくとも、運営手法や発注手続き等の執行段階改善余地があるものなどを、外部の会計土軍団と市の若手職員の混成チームで徹底的に洗い出して参ります。
2011年10月アーカイブ
とはいえ、奈良市では平成27年までに約111億円の財源不足が予想され、さらなる行革に取り組まなければなりません。昨年・一昨年と実施した事業仕分けでは、2年間で約25億円の財源捻出に成功しましたが、同じ手法がいつまでも通用する訳ではありません。そこで今年度は「事業・事務の総点検」と銘打ち、事業仕分けでは見えてこなかったムダなコストを徹底的に洗い直す作業に取り組んでいます。例えば、直接事業費はわずかであっても、膨大な人件費がかかっている事業をフルコスト基準で再評価を行う事、また事業目的は問題なくとも、運営手法や発注手続き等の執行段階に改善余地があるものなどをターゲットに、会計士をはじめとする外部の専門家集団と市の若手職員の混成チームで徹底的に洗い出して参ります。
奈良からはホテル・旅館の経営者や銀行・交通事業者等、実際に中国マーケットを狙う方々も同行し、現地のエージェントへの積極的な売り込みを行いました。奈良市としては初の試みでしたが、両市とも約30社のエージェントが参加し、さらにCCTV(中国のNHK)を始め多数のメディアに報じて頂く事ができました。
個人的に関心を持ったのは、現地の中学校の修学旅行ニーズです。既に旅行先を海外にシフトしている学校もあるようで、実際にイギリスや日本(鹿児島)などに修学旅行生を送客しているエージェントもおり、少子化で悩む日本の観光都市としては大変有望な市場であると感じました。当然、具体的なツアー催行にあたっては民間事業者が取り組む範疇となりますが、行政としては学校間交流などの部分でお手伝いできればと考えています。いずれにしても、今後の奈良観光の大きな方向性を感じた訪問であったのは間違いありません。
奈良市では先日、来年度の当初予算編成に関する基本方針を発表しました。例年10月ごろから翌年度予算の編成作業に着手をし、財政課・総合政策部長・副市長・市長と、各段階での査定を経て、来年3月の定例市議会に予算案として提出する流れとなります。今回の編成方針は担当課である財政課と何度も練り直し策定したものですが、その構成は5つの柱から成ります。以下、その概要です。
1)第4次総合計画の推進
平成23年度から10年間の奈良市の基礎となる総計に掲げている、まちづくりの基本方向に沿った事業計画・予算であること。
2)大幅な収支不足の解消
来年度から平成27年度までの財政見通しにおいて、約111億円の財源不足が生じる。これは、税収減による影響と、生活保護費を中心とする社会保障関係費の大幅増という、全国共通の厳しさに加え、奈良市の特殊要因として土地開発公社等の精算という「負の遺産」処理に要する財源を生み出さなければならないという厳しさがあります。市民への影響を極力抑えるためにも、徹底した事業・コストの見直しが必須です。
3)フルコスト視点での全施策の徹底した見直し
直接事業費だけに着目した従来の見直しではなく、施策の執行に係る人件費や間接費も含んだ「フルコスト」視点での見直しを行う必要があります。
4)戦略的な新規施策の提案
予算の削減、施策の廃止だけでなく、街の未来につながる新たな取り組みや既存施策の拡充についても、柔軟な発想で積極的に提案することを求めています。特に子育て・環境・観光の重点分野や、今後のニーズ増大が見込まれる領域での早期対応や予防的施策に力をいれることとしました。一方で、これらに要する財源については、既存施策の廃止や歳出削減、国県の補助やモデル事業の活用等の新規財源によって賄うことを原則としています。(いわゆるペイアズユーゴーpay as you go原則)
5)部内マネジメントの徹底
各部において、部長の強いリーダーシップによりメリハリのある予算編成を行うことを求めました。従来は部内の各担当課と財政課との間で予算折衝を積み重ねる手法が中心となり、部長が部内の全施策・予算を把握できていない状況も散見されました。今後は部長をトップに、市の予算や事業を部単位でしっかりと把握・分析したうえで、財政当局とのプレゼンに臨む形に変えました。今回の編成方針では、既存の継続事業に関しては前年度の90%を上限(シーリング)として見積もる事としていますが、これは機械的に一律カットを行うという意味ではなく、真に必要なものはカットなしもOK、その代わり他のコストをより大きく削減するといった裁量を部長に与え、部全体でのシーリングとしている点がポイントです。