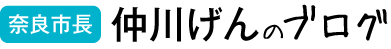本日は「なら・観光ボランティアガイドの会朱雀」の第10回総会に参加させて頂きました。法人化前を含めると15年に及ぶ活動の歴史は非常に重みがあります。いわゆる大量送客・大量消費型の観光から個人を中心とした滞在・交流型にシフトするなかで、ボランティアで奈良の魅力を伝える活動の広がりは今後の観光インフラの視点からも重要です。世界遺産の社寺というハードウェアに、歴史文化と言うソフトウェアが載り、さらにボランティアガイドや市民の「おもてなし」というヒューマンウェアが重層的に折り重なるというイメージです。これが昨年の1300年祭の成功要因でもあり、これからの新しい観光の形となるでしょう。
2011年5月アーカイブ
本日は「なら・観光ボランティアガイドの会朱雀」の第10回総会に参加させて頂きました。法人化前を含めると15年に及ぶ活動の歴史は非常に重みがあります。いわゆる大量送客・大量消費型の観光から個人を中心とした滞在・交流型にシフトするなかで、ボランティアで奈良の魅力を伝える活動の広がりは今後の観光インフラの視点からも重要です。世界遺産の社寺というハードウェアに、歴史文化と言うソフトウェアが載り、さらにボランティアガイドや市民の「おもてなし」というヒューマンウェアが重層的に折り重なるというイメージです。これが昨年の1300年祭の成功要因でもあり、これからの新しい観光の形となるでしょう。
毎年、開催しているタウンミーティングが始まっています。先週土曜は、午後から市役所正庁で南部ブロック(大安寺・東市・明治・辰市・帯解・精華)と中西部ブロック(都跡・平城・伏見・伏見南・西大寺北・六条校区)、夜は西部会館(市民ホール)で西部北ブロック(登美ヶ丘・二名・青和・平城西・東登美ヶ丘・鶴舞)を実施しました。今年のテーマは 「平成23年度予算と重点施策~子ども、医療、観光に重点を置いて未来への種まき」とし、市の財政状況や今年度新たに取り組む事業等についてご説明いたします。また、参加者の方々からの地域の声を直接伺い、市政に反映させる事を目的としています。さらに今回は、去る1月臨時議会で否決された「第4次総合計画の策定経緯」についても報告をすることになっています。今週末以降も、 各地域で順次開催しますので、ぜひご参加下さい。
・5月14日(土)13:30~15:00(受付:13:00~)
@奈良市役所
中央東ブロック(飛鳥・鼓阪・佐保・済美・済美南)
中央西ブロック(椿井・大宮・佐保川・大安寺西)
・5月28日(土)14:00~15:30(受付:13:30~)
@興東小学校(旧相和小学校)
東部ブロック(田原・柳生・大柳生・東里・狭川・月ヶ瀬)
・5月28日(土)19:00~20:30(受付:18:30~)
@都祁交流センター
都祁ブロック(並松・吐山・都祁・六郷)
・6月4日(土)9:45~11:15(受付:9:15~)
@北部会館(市民文化センター)
北部ブロック(神功・右京・朱雀・左京・佐保台)
・6月4日(土)14:30~16:00(受付:14:00)
@西部会館
西部ブロック(富雄・あやめ池・学園南・富雄南・鳥見・奈良帝塚山・学園三碓)
先週に引き続き、千葉市の熊谷俊人市長と共にBS11に出演し、基礎自治体としての震災対応について談義します。
コメンテーターは元経産省官僚で、東京財団上席研究員の石川和男さんです。
5月7日(土)8:00~9:00
BS11「石川和男のひざづめ談義 社会保障篇」
http://www.bs11.jp/news/1257/
水曜・木曜の二日間、友好都市の多賀城市と、姉妹都市の郡山市を訪問しました。3月11日の地震発生から現在まで、両市の市長や災害対策本部とは何度も連絡を取り合いながら、奈良市として可能な支援を続けてきましたが、やはり自分の目で直接現場を確認したいと思い実行しました。また両市の市民の皆さんに対し、遠く離れた奈良の地からも多くの市民が応援している事を伝えたいと考えました。今回の訪問には議会からも山本議長が参加されました。
まず始めに訪れた多賀城市では、約180名の方がお亡くなりになり、現在も約1000名の方が避難所生活を送っておられます。海岸から2~3km離れた市役所近くまで津波が押し寄せ、662haもの広範囲にわたり浸水被害が出ました。街中の家屋や建物には、津波の到達した高さが茶色い線でくっきりと分かり、まさに「街が沈む」というとてつもない状況を伝えています。一時に比べれば瓦礫も相当片付いた、と菊地市長も仰っていましたが、全6000台にも及ぶ被災車輌の撤去も未だ半数が残されているなど、本格復旧にはまだ時間がかかると思われます。


今回訪問した3ヶ所の避難所でも、「浸水被害と言っても、海底の泥や(流されたタンクローリー等からの)油も混じっており、掃除をしたぐらいではとても住める状態ではない」という声や、「家は集合住宅の高層階なので、なんとか住める状態だが、近所の商店が無くなり、車もないので歩いて30分以上買い物に行かなければならない」など、避難者の方、それぞれに事情が異なる事が良く分かりました。また、日中は子ども達が仕事や学校に出てしまい、高齢者が避難所で一人で留守番をする姿も見かけました。「何か役に立ちたいけれど、邪魔になってもいけないのでここにいる」という声に、やりがいや生きがいといった心の栄養も必要だと感じました。
多賀城市の職員の中には、家族を亡くされた方も多く、被支援者と支援者の境がない状態と言えます。地震発生から文字通り不眠不休で、一日一食で耐えた日もある、と市長から伺いました。そんな現地の職員を少しでも支えようと、奈良市から20名×5クール、計100名の職員を避難所運営支援に派遣しています。私が訪れたときはちょうど第一クールの2日目でしたが、既に業務内容を把握しキビキビと働く職員を見て少し安心し、そして誇りに思いました。3ヶ所それぞれで職員を激励し、次の訪問地へと向かいました。